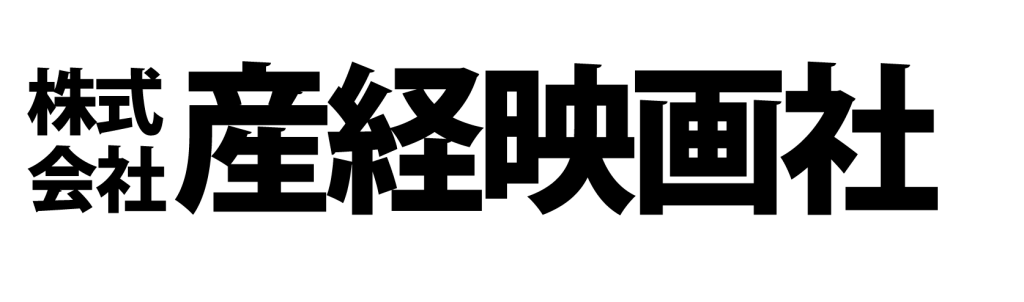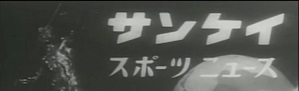晩秋の神宮の杜がオリックス・バッファローズの歓喜で揺れた。1996年、阪神淡路大地震の復興のシンボルとして仰木彬率いるブルーウェイブが希望を乗せた青い波となって長嶋巨人を飲み込んで以来の日本一だった。歓喜したのはオリックスファンは勿論、”近鉄好き”にとっても念願の載冠だった。戦後プロ野球がセパ12球団になる中、残念ながら日本一になれぬまま消滅した近鉄バッファローズ。そのシンボルマークは世界に誇る芸術家、岡本太郎さんのデザインだった。岡本太郎さんに、2度、直接、近鉄についてお話を伺う機会があった。自らのデザインを「グランドで燃え上がる勇猛な牛」と仰っていた。中学生時代耽読した金田一耕助シリーズ。原作者の横溝正史さんも近鉄を愛する一人だった。野球はチームスポーツだと知りながら、なんとなく「チーム」という集団を応援する気分が、正直、私は苦手だった。
1988年10月19日、あの日、川崎球場にいた。ロッテと近鉄のダブルヘッダー、第1試合が終わり、第2試合が始まろうとする時だった。デスクから手渡され足元に放置していた巨大な携帯電話が、初めて鳴った。「近くに西本さん、いないか?阪急が身売りだ」右後方の席にその顔が見えた。かつて大毎、阪急、そして近鉄を指揮した名将。それぞれのチームで個性的な男たちを育て上げリーグ優勝は果たすものの日本一だけは手に出来なかった悲運の監督。球界で最も狭い客席としても知られた川崎球場。人と席を縫うようにして西本さんの元に辿り着いた。ー阪急が身売りです。「ホ、ホンマか…」西本さんは言葉を失い第2試合に向けて整備が終わろうとするグラウンドを見つめていた。始まろうとする運命の一戦、終わろうとする関西の雄。
1989年10月12日。宿敵西武の本拠地で近鉄の主砲ラルフ・ブライアントがダブルヘッダーで4本のホームランを放ち西武に引導を渡した。翌朝、立川から特急に乗り新幹線で帰阪するブライアントに密着した。野茂が三振の山を築く度、大阪と東京を往復した。猛牛の呼び名にふさわしい、個性豊かな無頼漢揃い。初めてこの「男たちの軍団」、チームという名の集団を応援したいと思った。
宿敵西武との戦いの後、定宿のある立川の、キネマ通り辺りで酔いどれて、街を闊歩していた男たち。そして果たせなかった日本一。
2022年、実りの秋、猛牛が黄金色に輝いた。