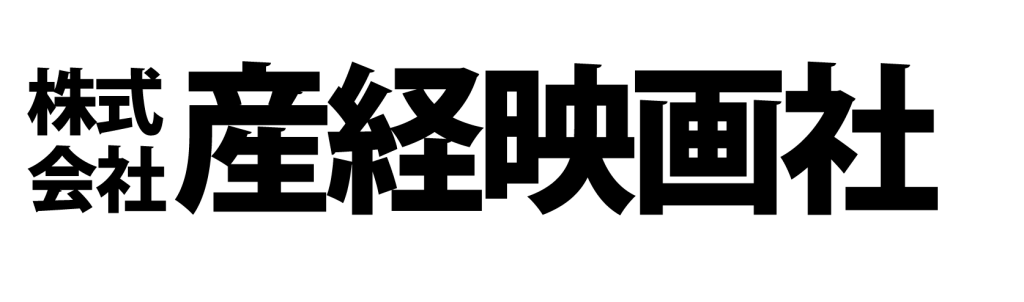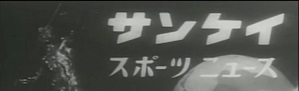ロシアのウクライナ侵攻は,未だ出口が見えない悲惨な戦いが続いている。
戦禍の中でアスリートたちの未来も揺れている。自ら銃を持って戦線に赴く者、そして非業の死を迎えた者。太平洋戦争の際、日本にも競技への復帰を夢見ながら、翻弄された多くのアスリートがいた。
戦争によって分断をされてしまった「スポーツという架け橋」
再び、異なる国と国、地域と地域、民族と民族、そして人と人を繋げる事は容易ではない。それを、ライブラリー映像の編纂をしながら痛感している。
太平洋戦争後の昭和26年(1951年)7月テニス・デビスカップ。
熊谷一彌監督率いる日本代表の3選手が(隈丸次郎・藤倉五郎・中野文照)ケンタッキー州ルイビルに渡った。真っ白な揃いのウェアで誇らしげにコートに立った日本代表をアメリカの観客が拍手で迎える。試合は日本のストレート負け。敗れた瞬間、日本選手は、対戦したアメリカ選手に駆け寄り、満面の笑顔で握手を求めていた。その姿から、再開となった国際大会への喜びが痛いほど伝わってくる。
ラグビーはその翌年、昭和27年(1952年)9月「秩父宮ラグビー場の柿落とし」が契機となった。秩父宮様が留学先でもあったオックスフォード大学を戦後初めて日本に招き、慶応大学と親善試合が行われた。銃をボールに変えて、両国の青年たちはぶつかり合った。
同じ年、ボクシングの白井義男がダドマリノと後楽園球場で世界タイトルマッチを行った。列島を熱くした戦いで白井義男が日本人初の世界王者を手にした。
そして、マラソンは終戦から9年後の昭和29年(1954年)12月鎌倉で行われた金栗賞が国際大会の再開となった。稲村ケ崎を通る雨の中の戦いを制したのはヘルシンキ五輪の銀メダリスト、レイノルド・ゴルノ(アルゼンチン)だった。
国家の乱暴な決断は、有望な才能の、貴重な時間と可能性を、どれほど奪い取ったのか。
「自称 柔道家」に、襟を正して考えて欲しい。