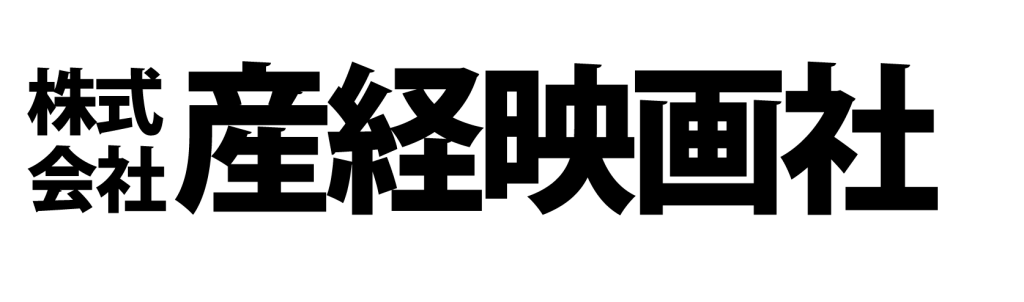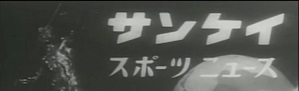オリンピック競技の競技数が増えることで、大会自体が巨大化し、資金集めの為に、税金が投入され、不透明な運営に疑念が膨らみ、人々から五輪のへの情熱が失われていく事、それは本意ではない。一方で新しい世代が、新しいスポーツに親しみ、新しい価値が生まれることも、大きく構えれば人類の進化の一歩。かつて北米辺りのネイティブアメリカンが嗜んでいた遊びが、国境と民族と言語を超え、人々に愛される。これまたスポーツの持つダイナミズムである。ラクロスは日本上陸当時はキャンパス・スポーツだった。20世紀の後半、1985年頃、慶応義塾大学を中心に首都圏の大学から一気に全国へと広がった。当時、原宿や渋谷ラクロスの「クロス」を手に闊歩する女子大生の姿は新鮮だった。ラクロスは男子と女子で大きくルールが違う。出で立ちも男子はアメフトの様なヘルメットとプロテクター、そして剣の如きクロス。一方、女子は足元も軽やかにスコート姿でフィールドを駆けゴールを目指す。現時点の日本の競技人口は約18,000人。男子が約5,500人、女子は12,500人。女子の競技者が男子の約2倍!1980年代にプロレスラー長与千種さんにラクロスを体験してもらったが女子はコンタクトがないため、レスラーとしての武器を生かせず走り回られて終わってしまった。約40年、ラクロスはキャンパススポーツとして学生たちの間で磨かれ日本独自の歴史を積み上げてきた。今月、大田区にある大井ラクロス場で男女の全日本クラブ選手権が行われた。そこにキャンパススポーツ、ラクロスならではの場面があった。男子優勝のグリズリーズ、女子優勝のneo、共に試合終了の歓喜の後、選手・スタッフ全員が客席に向かい整列しキャプテンが地声で、優勝の喜びと、応援への感謝と、相手へのリスペクトを「自分の言葉」で語った。簡にして潔。冬の夕日に染まるフィールドに熱い思いは、響いた。20世紀の終わり頃に始まった日本のラクロス。学生たちが育み、築いた日本ラクロスの誇るべき習わしだ。現在、日本の世界での実力は男女共に5位あたり、五輪でメダルを狙える位置にいる。4年後、ロサンゼルスで習わし通り「勝利の声」を聴くことが出来たら…。やはり新競技には、無限の夢が詰まっている。
MENU
スポーツ毒と倫 doctrine
- HOME »
- スポーツ毒と倫 doctrine »
- へらずぐち »
- 「ラクロス」キャンパス・スポーツから五輪競技へ